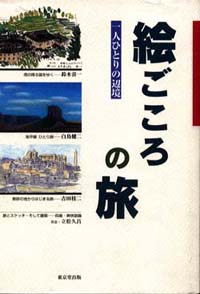|
アユミギャラリー出版取り扱い書籍の紹介 |
AYUMI GALLERY |
|
|
■絵ごころの旅 内容紹介 この本は、三人の絵を集めた絵本です。しかし、ただ単に絵を集めたものではなく、「辺境」をテーマにしています。絵は、三人がそれぞれ辺境の地へおもむきその土地に住んでいる人や家の中などを見て、記録されたものです。旅の楽しさ、絵を描く楽しさが伝わる本です。 |
□旅に出かけたくなるいくつかの本
……藪野 健 (画家・武蔵野美術大学教授)
僕にとって旅とは絵を描くことである。砂漠を歩くことも、町なかの雑踏もそれに記憶の中の風景もある。だから旅の本となるとつい開いてみたくなってしまう。なかでもいくつかの本が心を掴んで離さない。『絵ごころの旅』は3人の建築家のいわば画文集あるいは絵日記の形をとっている。ところが「一人ひとりの辺境」と副題にあるように、ただごとではない。
「雨の降る国をゆく」(鈴木喜一)、「地平線ひとり旅」(白鳥健二)、「熱砂の地から」(吉田桂二)と何れも描き難く、帰り難く、かつ生き難い地がふくまれる。
旅は困難さが伴う程、豊かなように思える。快適さと不愉快さの微妙なバランスが緊張感をもたらし、そのため感性はとぎすまされる。
吉田桂二が記しているように「人間の命は自然に預託されている、という生命の原点を感覚的に分かる」のだ。
絵を描いていて土地の人々から反感をもたれることは少ないがそれでも聖域や紛争地帯は別だ。白鳥健二がニューメキシコ州のネイティブ・アメリカの集落ズーニ・プエブロでスケッチを没収された時やシリアのダマスクスの集落で警察に突然銃口を向けられた時の暗い気持ちがよくわかる。「自分が今、どこにいるのかということを常に忘れてはいけない」とは辺境の、異文化の地でスケッチする場合の心得にしたい。実際描くこともあるいは居ることさえ生命がけになることだってある。あるいはそんな思いをすることがあるため、まなざしも感性もより研ぎ澄まされるのだろう。
そんなこともあって快くデッサンがすすむ時の喜びはひとしおだ。グアダラハラの描かれた人々の生き生きとしたことはどうだろう。
鈴木喜一の福建省永定県の客家土楼を描いた一連のデッサンは画中を見る楽しさに読む楽しさが加わる。筆談の「<瞭望台土楼的軍事防御施設、四層土楼、一楼的厨房二楼的粮倉三四楼的臥室>、<坑地震、防風、防火、防盜、冬暖夏涼>」が納得できる。
「土の家は外に堅く、内に柔らかい。人が集まって住むことの楽しさ、助けあう形、協同の強いつながりを内なるパブリックな空間に思うことができる」と語っているが、空き家が年々増え、崩れかかっているのもあって文明がこの地にもしのびよってくることへの嘆きが伝わってくる。
「耳を澄ませていると人の話し声や歩く音がよく聞こえる。鶏、あひる、豚、鳥、カエル、猫、犬、虫の鳴く声、子供の泣き声なども響いてくる」。
これは住宅が本来もつべきもので、現在の住居が失ったものではないだろうか。
「振成楼環形土楼外観」の絵の空のにじみはまるで、消えていくものへの悲しみのようにみえる。
吉田桂二のスルタン・ハサン・モスクの絵を見ながら十数年前のことを思い出していた。発掘調査のためエジプトのナイル河畔の町で2ヶ月近く滞在したことがあった。
ミナレットから真夜中を含む定時刻に町中に鳴り響くコーランの朗詠に、初めは驚いたが、しばらくすると快い響に変っていった。それは町なかの迷路についてもいえる。毎日歩いているうちに、何処もある規則性を感じることができた。「自然発生的にそうなったと思いがちだが、実は、コーランで規定された原則性によって、極めて意図的に造られた町なのだ」と実感した。
迷路の町で絵を描いていると、旅は帰ってこそ旅なのだが、時にはもう帰れないのではないかと思うことがあった。体力も気力も限度があって、それを越すと幻覚とも夢ともつかぬ気分となる。
吉田桂二が語るように「イスラム教の原理の激しさの中には柔和な風土に住んできた民族とは違う、砂漠に生きる民族の心意気を見ることができる」とともに辺境の地をものともせず、描きかつ書き続ける3人の心意気が感じられてならない。
ことにそれはこの本の最期の章に表れる。3人と立松久昌の談論だが、これは絵を描くことの意味と目的が明確に語られている。
吉田「ぼくは〈建築家なら絵を描け〉と言いたい。〈絵を描けないヤツが建築の設計をするな〉と言いたいですよ」。
これには仰天してしまう。ふと「建築をつくれないヤツが絵を描くな」と言いかえてみるとその発言の強烈さがわかる。4人が語り合っていることは一見なごやかにすすんでいるが実は重い意味をもっている。
立松「何不自由なくねぇ……。我々の世代では『自由』って言葉を使う時に『不自由』って言葉の裏返しの形で標榜するんだな。特に吉田桂二さんと私は同い年ですから、中学三年生の時に第二次世界大戦が終わり、日本は負けるわけです。戦争という時代からやっと解放された中で、私らは子供ですから、回復力があるわけです。むしろ、大人たちの方が痛んでたよね。大人が無口になってましたよね。精神的に傷ついた人もあってね。
しかし、平気だった人も大勢いたために、日本が戦争に負けたことについての反省が、今だもって少ないってことを思ってますがね。
それぞれそういう世の中に依拠しながら、私たちは時代の自分化を心がけてきたと思うんですよ」。
これはまなざしが何処に注がれなくてはならないか、出発点が何処なのか、自分が何処に居て、何なのかと言うことだし、それが語られなくていいのかという警告でもある。
「旅をするとね、異文化をみるまなざしが深くなる」の言葉は、「戦争があるとね、自分たちの現在をみるまなざしが深くなる」とも読みとれる。この本の「旅」の言葉は他の言葉に置き換えてみると、意図がみえてくる。
「死ぬまでそれぞれの旅を続けようじゃない。そして描き続けるし、造り続ける」のだと。
(中略)
辺境、都会、地方、対象は違っていてもさまざまな出逢いの旅があるように思う。まずは旅に出かけなくては。旅の数冊とスケッチブックをもって。